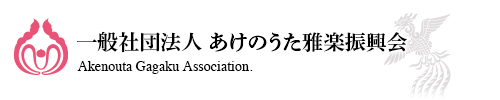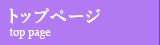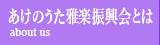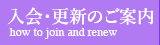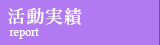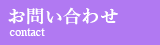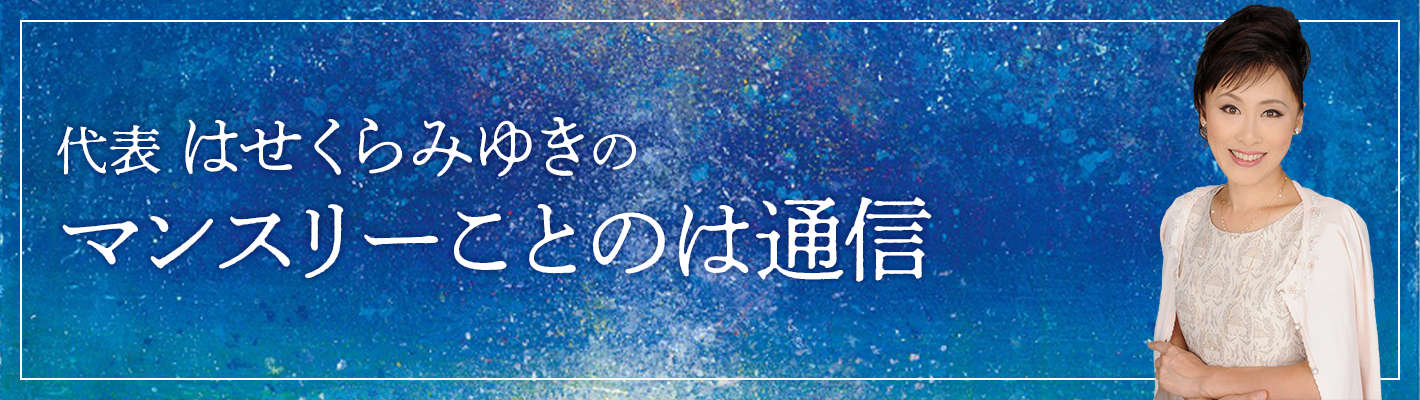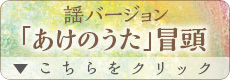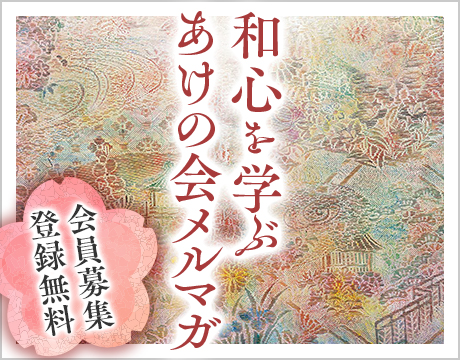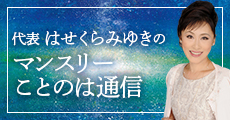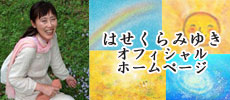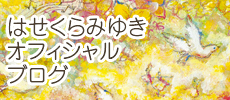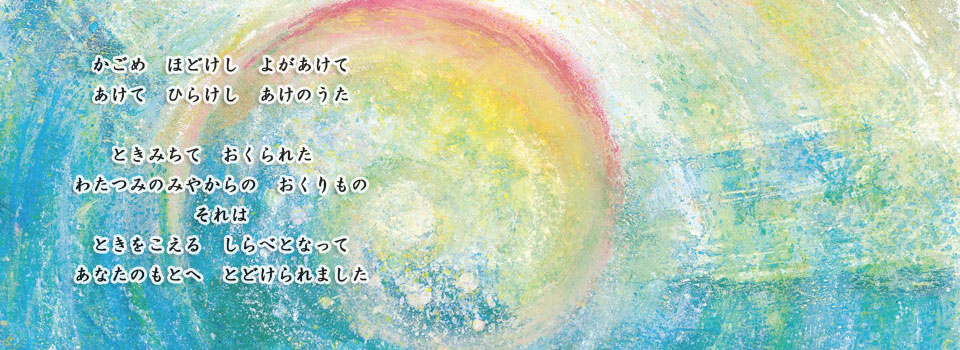
あけの会 マンスリーことのは通信2025年1月
新年、明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、佳き新年をお迎えされていることと思います。
今年も安らかで良い年になりますよう、祈念しております。
さて、私の方は、孫も含めた家族が集まったので、
オーガニックおせちを手作りし、穏やかなお正月を迎えました。
あんこは小豆を炊いて、麹と共に発酵させた発酵小豆。
そうするとお砂糖いらずで甘くなるので気に入っています。
また、黒豆と花豆(大きな豆です。北海道十勝産)を煮ました。
甘みは、オリゴ糖とデーツに少量の塩を加えて調整しました。
孫も美味しそうに食べてくれて嬉しかったです(しっかりばぁばしています…笑)
また、久々にお肉も触って(笑)、手作りのハムをつくりました。
ハムは鳥ハムで、塩麹に一晩つけた胸肉をクッキングシートでまいて、
タコ糸でぐるぐるまきつけて5分ゆでて放置しておくだけ。
すると胸肉あるあるのぱさぱさにもならず、
しっとりさっぱりして美味しいのです。
…というわけで、お料理のお話からはじまりましたが
昨年同様、皆元気で、時を過ごせることがなんと有難いことかと思います。
そんなお正月、とりわけ元旦の日は、「年神様(としがみさま)」と呼ばれる、
新年の神様が一年の幸福をもたらすために各家庭に降臨するといわれています。
年神様の正体はどなたかご存じですか?
それはご先祖たちの神様―「祖霊神」なのです。
他にも、田んぼの神や山の神として崇敬されております。
そうした年神様は、五穀豊穣や子孫繁栄、健康や幸福を授けてくださる、
有難き神様であり、別名、お正月様とか歳徳神ともいわれているのですね。
そんなお正月には「おせち料理」をいただきますが、
このベースにある考え方が、「神人共食」です。
神と人が共に同じものをいただき、箸を使って橋渡しをして天地共に栄えていく。
神の氣を受けた人と神々が一つになって、
共存共栄していくといった世界観を内包しているのです。
なお現代のようなお正月のスタイルは、江戸後期から始まり、
明治時代にかけて確立していったようです。とはいえ、
お正月の考え方や風習は、6世紀半ばにはすでにあったといわれています。
さて、年頭でもありますので、
ここで少し神道における考え方―思想について触れてみたいと思います。
神道には、「常若」(とこわか)という考え方があります。
常に清らかで若々しいさまをさす言葉です。
まさしく年を改める「お正月」は、常若であり続けるための、
大事な風習であり、伝統であるといえます。
この「常若」の他に、あと二つ、中軸となる考え方があります。
それは、そして明るき清き誠の心でいる大切さを指す「清明正直」。
さらに、日ノ本の国の根幹思想である
やわらぎの心―「和」を有しています。
あけの会はこの「和」の心を中心に、舞楽や研修などを通して実践し、
より深く理解すると共に、次世代へと引き渡していきたいという思いをもって
活動を続けております。
今年は11年目という新しい一歩の年であり、
秋には伊勢神宮の奉納も控えておりますので、
気持ちのいい緊張感と共に、魂が喜んでいるのを感じます。
会の活動にご興味のある方は、時折一般募集の枠もありますので、
そちらにご参加いただきながら、会の様子などを
体験されてみられるのもよいかと思います。
その節はよろしくお願いいたします。
それでは今月の雅楽をご紹介いたします。
以前にもご紹介いたしましたが、
やはり一月なので、やはり我が国の国歌―雅楽版の君が代を、
お届けしたいと思います。
舞楽となっている君が代は、
一糸乱れぬ舞のたおやかさと高貴さに、思わず息をのんでしまいますね。
また、もう一つ、日本紹介のビデオのような動画も、
面白いのでよければどうぞ。
(君が代の翻訳も歌と共に掲載されているのが新鮮です)
それでは本年も何卒宜しくお願い致します。
どうぞお体に気を付けて、お元気でお過ごしくださいませ。